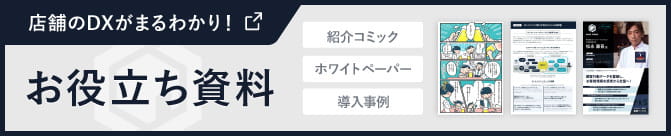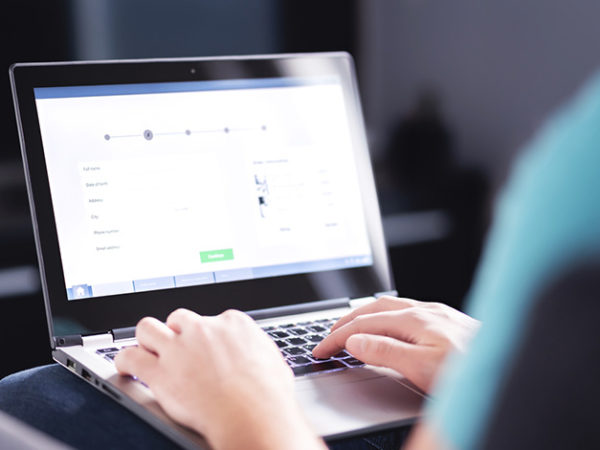顧客の満足度を調査するのは、現代では当たり前の手法になっていますが、「企業に対する信頼度・愛着度」までアンケートで調査できるのはご存じでしょうか。企業に対する信頼度・愛着度を調べる際に利用するのが「NPS」です。今回は、このNPSのアンケートについて詳細を解説していきます。
NPSのアンケートとは?

NPSとは「企業・ブランドに対する顧客の信頼度や愛着度の指標」です。正式名称は「Net Promoter Score (ネットプロモータースコア)」といいます。NPSはアメリカのコンサルティング企業が利用を開始したのを皮切りに、AppleやAmazonなど世界中の大手企業で導入が進んでいます。日本企業も例外ではありません。日本企業の約10%がNPSを導入しているとされています。企業に対する信頼度・愛着度は、これまで数値化するのが難しかったですが、NPSの登場により具体的に把握することが可能になりました。顧客のニーズが多様化している現代社会では、抽象的な情報やデータを可視化していくことで、セグメントを詳細に分けていくことが可能です。NPSは各種マーケティング施策にも生かすことができるといえますね。
NPSを測るためには、顧客から直接意見を集める必要があります。インタビューを行って直接情報を集める方法もありますが、一般的なのはアンケートを利用した情報収集です。アンケートであればオンライン環境でも実施することが可能で、情報量もインタビューより充実させることができます。SNSやアプリを利用してNPSのアンケートを実施することもできるので、調査会社に依頼せずとも情報を集めることが可能ですね。
NPSのアンケートの作り方

NPSのアンケートを作る際は、下記のポイントをおさえることが肝要です。
- 質問数はなるべく少なくする
- 質問内容は簡潔にする
- 選択形式に加えて、記述式の項目も設ける
質問数はなるべく少なくする
まずポイントになるのが「質問数」です。NPSを測る際はなるべく質問数を少なくすることが重要になります。質問数が多くなると、後半にいくにつれて回答の精度にブレが生じる可能性があります。あくまでも「企業への信頼度・愛着度」を数値化するためのアンケートなので、質問数を多くして詳細に情報を集める必要はありません。質問数の目安は4~8問ほどで、5分以内に回答できる量を心がけましょう。
質問内容は簡潔にする
質問内容は短く簡潔に設定します。これも質問数を少なくするのと同様の理由で、長くなりすぎると回答者が読む気を無くしてしまい、回答の精度が下がってしまう可能性があるためです。「0~10点の間で答える」など、数値を選べるように設定しておけば、回答者も直感的に選ぶことができます。
選択形式に加えて、記述式の項目も設ける
選択形式の質問に加えて、記述式の質問も数問入れておくとアンケートの精度を高められます。たとえば、「数値を選んだ理由」を記述式で書いてもらえば、なぜその数値を選んだのか情報を集められます。また、意見・要望を記述形式にすれば、顧客から直の情報を集めることができますね。
NPSアンケートの計算方法

NPSアンケートを集めた後、各アンケートの点数によって、
- 批判者(1~6点)
- 中立者(7~8点)
- 推奨者(9~10点)
の3つのカテゴリーに分けます。各カテゴリーに属している人は、おおむね下記の特徴を持つとされています。
- 批判者
→「企業に対してマイナスなイメージ・意見を持っていて、他の人に企業の悪いイメージ・意見を伝えてしまう可能性がある人物」 - 中立者
→「企業に対して特段マイナスなイメージ・意見は持っていないが、他の人に企業を薦めることもない人物」 - 推奨者
→「企業に対する信頼度・愛着度が高く、他の人に企業を薦めてくれる人物」
NPSは、回答者全体の「推奨者」の割合から「批判者」の割合を引くことで算出できます。
NPS=回答者全体の「推奨者」の割合-回答者全体の「批判者」の割合
たとえば、推奨者の割合が70%、批判者の割合が10%の場合は、
NPS=70-10=60
となります。
NPSの数値範囲は、-100~100の範囲内になりますが、数値は絶対的なものではなく、あくまでも相対的なものです。他社のNPSや業界平均のNPSと比べて、自社のNPSを見ることが重要です。得られたNPSの数値に加えて、アンケートの記述回答も合わせて分析することも肝要ですね。
NPSアンケートと顧客満足度アンケートの違い

NPSのアンケートと混同しやすいのが顧客満足度アンケートです。両者ともに顧客の意見を集めるアンケートになりますが、両者は下記の点で違いがあります。
- 調査の対象
- 継続調査の向き・不向き
調査の対象
顧客満足度アンケートの場合、調査対象は「具体的な商品・サービス」となります。調査対象の範囲が狭いほど、適正な意見を集められるのが特徴です。ただし、顧客満足度アンケートは「企業全体のイメージ」を調査するのには適していません。NPSアンケートの場合は、点数化した数値から企業全体の評価へ還元することができるので、全体的なイメージ調査に向いています。
継続調査の向き・不向き
継続して調査を実施した場合、顧客満足度アンケートだと長期的な付き合いのある顧客からは「とても満足している」もしくは「全然満足していない」という両極端の評価に偏る傾向があります。これは心理的な要因でもありますが、長期的な付き合いがある分、評価の方向がどちらかにブレてしまうのです。NPSアンケートの場合は、多少評価がブレたとしても、数値自体が変わるケースは少ないので、期間を問わずに実施することが可能になります。継続的な調査にもNPSアンケートは向いているといえますね。
NPSアンケートを活用して、企業のイメージアップを図ろう
NPSアンケート活用することで、企業に対する顧客の信頼度・愛着度を測ることができます。企業への信頼度・愛着度は抽象的な概念であったため、これまで数値化することが難しかったですが、NPSの出現によって具体的に把握することが可能になっています。NPSアンケートの作り方はそこまで難しくありません。5分以内で回答できる範囲の問題数、簡潔な質問文、選択した理由の記述を設ければ簡単に作成できます。問題数を多く設定したり、質問文を長くしてしまうと回答の精度が安定しなくなるので、注意してください。調査期間によって結果が大幅にブレることも少なく、長期的な調査にも向いています。NPSアンケートを活用して、企業のイメージアップにつなげていきましょう。
無料ホワイトペーパー:「常連さま」の作り方とは?

既存顧客の定着をどうやって実現したらいいのか分からないと悩んでいませんか?本書では、以下のことについて詳細に解説しております。
- 商品の質が良いだけでは経営は安定しない
- なぜ顧客中心のマーケットインの発想が求められるか?
- いま必要なのは、マーケティング、ブランディング、CRM強化!
- そのために必要な施策
ぜひ、「常連さま」を作るための情報収集としてご活用ください。