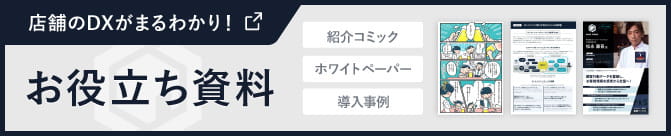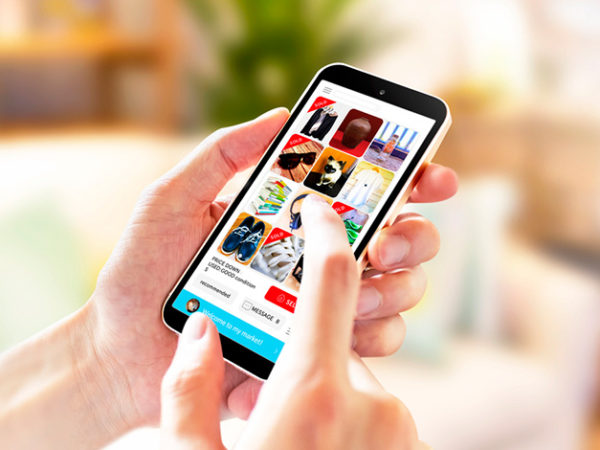あなたは「NPS(ネットプロモータースコア)調査」をご存知でしょうか?NPSとは「自社ビジネスの顧客ロイヤルティを測るための指標のこと」です。企業の収益性や成長率との相関が高く、Appleをはじめとする世界中の企業でNPS調査が導入されています。この記事では、NPS調査について解説します。
NPS調査とは?

NPS調査とは、自分の会社の事業及びビジネスの顧客ロイヤリティを計測する指標である「NPS(通称:ネットプロモータースコア)」の調査を行うことです。もともと、顧客(生活者)が企業やブランド等に対して「どれくらいの愛着・信頼を持っているか」に関しては、街中でのヒアリング調査やインタビューなどで肌感を知ることはできても、「◯%」というように数値化するのは難しいと思われていました。しかし、NPSであれば、それらの感覚値を数値化できます。つまり、顧客(生活者)が企業やブランド、商品・サービスにもつ愛着や信頼感を測ることができるのです。
NPS調査は、非常にシンプルな構成になっています。まず、顧客に対して「親しい友人・知人に企業や商品・サービスをどのくらいおすすめしたいか」について11ステップの評価アンケート(数値は0~10点)を実施します。そのアンケート結果からNPSを導きます(詳細は後ほど)。質問自体はシンプルなのですが、そこから導き出されるNPSは企業やブランドにとって大きな意味を持ちます。なぜなら、NPSは「企業の業績(収益性)や成長率との相関が高いから。言い換えると「NPSの数値が良い企業やブランドは、業績・収益性も良い傾向にある」ということなのです。このようにNPS調査は、自社ビジネス及び事業の「現状」を測る良質な方法として、世界のさまざまな企業で導入が進められています。
NPS調査には2種類ある

一言でNPS調査と言っても実は2種類のNPS調査があります。それはリレーションシップNPS調査とトランザクショナルNPS調査です。それぞれどのような調査なのか解説していきます。
リレーションシップNPS調査
リレーションシップNPS調査は、主に会社のブランドや商品に対してロイヤリティを調査することです。商品やサービスの問題点を発見し改善に活かすことができます。自社内で商品の問題点を見つけるだけでなく、他社の商品と比較を行うことで客観的に自社商品のメリットやデメリットを見つけられます。また、リレーションシップNPS調査は定期的に行うことが効果的で、長い目で見ればデータ収集ができ商品開発の参考にできます。
トランザクショナルNPS調査
対して、トランザクショナルNPS調査は店舗や営業者に対して調査を行うことです。リレーションシップNPS調査に比べてより具体的に調査し改善点を見つけることが可能です。店舗や営業担当者に関するアンケートを顧客に答えてもらうことで、調査を行えます。アンケートを行う場をわざわざ用意しなくてもお店アプリから顧客の声を集めたり、メールでアンケートを配信することで簡単に情報を集められます。トランザクショナルNPS調査も定期的に行うことが有効です。
NPS調査と顧客満足度調査の違い
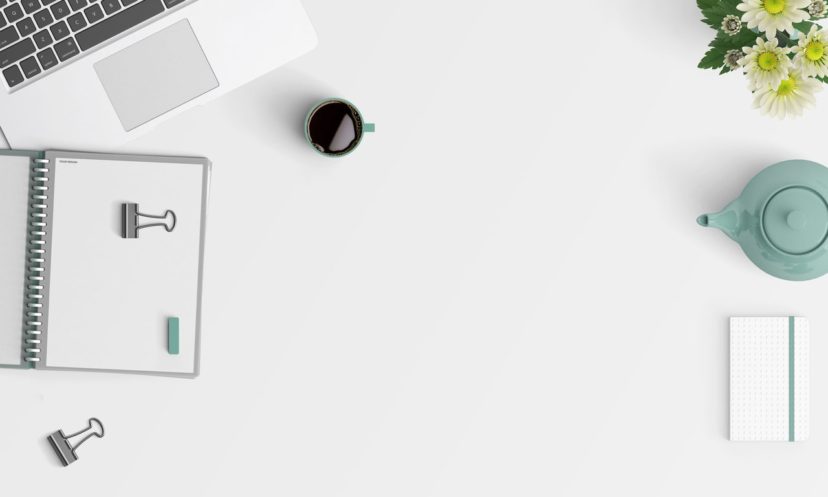
NPS調査で計測される「NPS」の指標。これと並ぶ指標としてビジネスにおいてはしばしば「顧客満足度」が挙げられます。まず、顧客満足度について整理しておきましょう。
顧客満足度というのは、簡単にいうと、自社ビジネス・事業を使ってくれる人が商品・サービスに対して「どれくらい満足してくれているのか?」を示す指標です。一般的に、顧客というのは「自分が商品やサービスに対して思い描いた水準(=期待値)を上回る」場合にのみ、「このサービス良かったなぁ」と高い満足感を得る傾向にあります。サービスに満足した顧客は、リピーターになったり、友人・知り合いにサービスを紹介してくれたりすることもあるでしょう。そして、顧客満足度を上げることで結果的に売上につながる可能性もあります。
では、NPSと顧客満足度の具体的な違いはどこにあるのでしょうか。それは「業績との相関性」です。顧客満足度調査では、「顧客満足度」つまり「顧客がどれくらい満足しているのかか」を計測します。しかし「満足」という言葉は非常にあいまいなもの。先ほど「顧客の満足度を上げることで売上につながる可能性がある」と表現しましたが、必ずしもそうなるとは限りません。一方、NPSについては、企業の業績(成長率)の間に高い相関関係があることが様々な調査や論文等で証明されており、「NPSのスコアを向上させることで業績向上につながる」と言い切ることができます。この点が、NPSと顧客満足度ないしNPS調査と顧客満足度調査の大きな違いになります。
NPS調査の計算方法

NPS調査では、以下のようにしてNPSの値を算出します。
1.商品・サービスを知人におすすめする可能性についての質問を行う
ある企業・ブランドのサービスや商品を利用している顧客に対して「あなたはこの企業(商品、サービス、ブランドなど)を友人・知人、同僚などに進める可能性はどれくらいありますか」という質問を行い、「0〜10点の11段階」で評価してもらいます。
2.顧客タイプの分類
上記の質問の回答・評価に応じて、以下の3つの顧客を分類します。
- 推奨者:9〜10点をつけた顧客
- 中立者:7〜8点をつけた顧客
- 批判者:0〜6点をつけた顧客
ちなみに、「推奨者」はリピート率(再度、商品を購入したり、サービスを受けたりする可能性)が圧倒的に高く、いわゆる商品・サービスの「紹介者」に当たるのがこのタイプです。逆に「批判者」は、わかりやすい言葉で言うと「アンチ」。ネガティブな口コミで、商品やサービスに関するマイナスイメージを与える可能性があります。
3.顧客タイプ別のデータをもとにNPSを算出する
ここまでデータを集められればNPSの算出はシンプルに行うことができます。質問の回答者全体に占める「推奨者」の割合(%)から、「批判者」の割合を引いた値が「NPSのスコア」になります。わかりやすくするために「1,000人にアンケートを行った場合」を考えます。例えば、「推奨者」の数が500人、「批判者」の数が300人だった場合、推奨者の割合は全体の50%、批判者の割合は全体の30%です。NPSのスコアは、「(推奨者の割合)-(批判者の割合)」なので、「50%-30%」。つまりNPSのスコアは「20(%)」となります。当然、推奨者の数が多く、批判者の数が少ないほどNPSのスコアは上がります(範囲は、「-100」〜「+100」まで)。
企業・ブランドがNPS調査を行うべき3つの理由
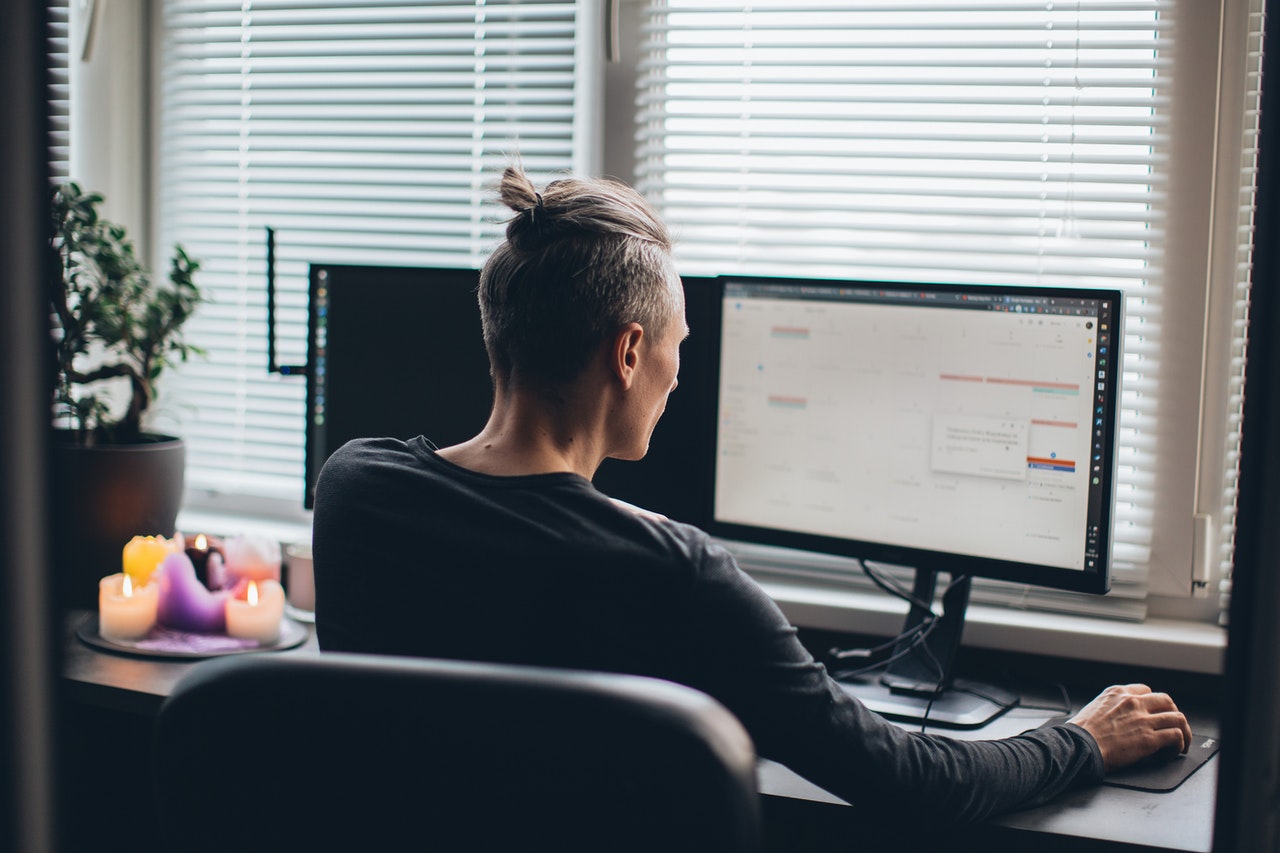
なぜ、NPS調査を行うべきなのか、その3つの理由を解説します。
1.NPSの改善が業績UPにつながる
NPSは、業績・売上と高い相関があるため、NPSのスコアを上げていくことで効率的に業績UPにつなげることができます。NPSと業績の相関に関しては、Satmetrix社という海外の会社が重要なペーパー(ホワイトペーパー「POWER BEHIND A SINGLE NUMBER」)を出しています。いくつかの業界において、合計400社を超える企業(ブランド)に対して、15万人を超える人々を対象にした評価を分析したところ「相関係数0.7」という強い相関が出ています。
2.NPSはKPI(重要業績指標)として活用しやすい
NPSは、KPIとして利用しやすい指標です。とくに社内横断的なプロジェクトやあるサービスに関わる部門全体など「全社統一のKPI」として定めることで、社内全体で連携して目標達成に向けて動くことが可能になります。もし、プロジェクト間の連携・コミュニケーションに課題があれば、NPSの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
3.NPSは簡単に作成・実施できる
NPS調査では、「商品・サービスを友人・知人におすすめしたいと思いますか」というシンプルな質問が使われます。これは、顧客ロイヤリティを調査する最も適した質問として全世界のNPS調査に採用されています。質問が決まっているため、NPS調査は簡単に実施できます。
NPS調査をうまく活用する方法

ここからはNPS調査をうまく活用する方法を紹介します。NPS調査を実際に行う際の参考にしてください。
トップのコミットメントが重要
会社のトップ、つまり経営者のコミットメントが大切です。会社全体でなぜNPS調査を行うのか、なぜ利益に繋がるのかを確認し、従業員に説明します。NPS調査は会社で一丸となって取り組むことが重要となってきます。
社内定着への仕組みを作る
長い目で見て、社内へ定着させる必要があります。一度調査を行うだけで満足せず、定期的に継続して調査する仕組みの構築が、成功へとつながります。
批判者が適切な顧客か見定める
批判的な顧客の存在はコストがかかる要因となります。自社のファンに変えるべき批判者か見極めることが大切です。そもそも商品のターゲット層と異なる顧客には商品の購入を促さないことも批判的な顧客を減らす方法の一つです。
商品開発する際のヒントとして活用
NPS調査は新たな商品開発のヒントになります。自社の人間が気づいていないところに顧客が注目している可能性もあるので、注意深く見てみましょう。
比較して自社のポジションを確認
他社と比較して、市場での自社の立ち位置を把握することもできます。他社と比較することで商品やサービスの改善に活かせます。
NPS調査で注意すべきこと

日本人の傾向
近年、日本の企業でもNPS調査を導入する企業が増加しており、業績や収益性の改善に利用されています。しかし、海外の企業と比較して、日本でNPS調査を行うと「値が低い」もしくは「マイナスな影響が出る」と言われることが多いです。実際にSatmetrixの調査では「日本は、他国に比べ顧客ロイヤルティの点数を低くつける傾向にある」と報告されています。これは、日本の企業やブランド、商品・サービスに問題があるわけではなく、日本の「国民性」が影響しているからなのです。基本的にはNPSに地域性や文化的要因は影響しませんが、日本に限っては文化的な要因がNPSの値を下げている可能性があると、ベイン・アンド・カンパニーのロブ・マーキー氏が言及しています。確かに、私たち日本人は誰かに意見を伝えるときに、直接的な表現はせず、少し間接的かつ遠回しな表現をする傾向があります。ただ、NPSのスコアの「絶対値」はそれほど気にする必要はありません。3ヶ月前と比べてNPSのスコアが伸びている、というように時系列で自社のビジネスの伸びを把握する指標として使うものだからです。継続的なNPS調査により、少しずつ顧客体験の改善を進めていくことが重要です。
無回答の顧客
顧客全員にアンケートを促しても、中には無回答の顧客もいます。調査に基づいて商品を改善する場合は、そのような無回答の顧客の存在を考慮する必要があります。回答者が少なければ偏った意見である可能性もあるからです。
法人向け調査での工夫
法人向け調査では工夫が必要です。回答者を「意思決定者」にするのか「利用者」にするのかを定めましょう。また、アンケートは短い時間で行えるものにして、気軽に答えてもらえるようにします。短い時間でできるアンケートにも答えてもらえないときは、日頃からの関係性に問題があるかもしれません。
まとめ:NPS調査を自社の業績アップに生かそう
この記事では、NPS調査について解説しました。
記事のポイントは以下の3つです。
- NPSとは、自社ビジネスの顧客ロイヤリティを測る指標の1つである
- NPSと企業・ブランドの業績や売上成長率の間には強い相関関係がある(NPSのスコアが高ければ、業績も上がる)
- NPSは、質問者全体の数に占める推奨者(9〜10点)の割合から批判者の割合(0〜6点)を引いて算出する
繰り返しになりますが、NPSスコアの改善に努めることで、企業やブランド、商品・サービスの業績(収益性)の向上につなげることができます。NPS調査自体は簡単に実施できますが、それを売上UPにつなげるためには、継続的な数値計測と全社的なNPSの理解が必要です。NPSを使って業績UPを目指してみてはいかがでしょうか。
無料ホワイトペーパー:「常連さま」の作り方とは?

既存顧客の定着をどうやって実現したらいいのか分からないと悩んでいませんか?本書では、以下のことについて詳細に解説しております。
- 商品の質が良いだけでは経営は安定しない
- なぜ顧客中心のマーケットインの発想が求められるか?
- いま必要なのは、マーケティング、ブランディング、CRM強化!
- そのために必要な施策
ぜひ、「常連さま」を作るための情報収集としてご活用ください。