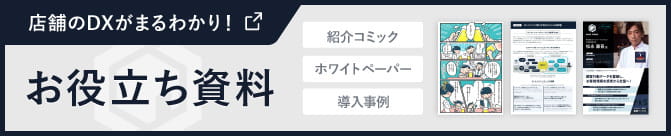経営層の方やマーケティング担当の方、マーケティングを正しく行えているでしょうか。マーケティングを上手く行い商品やサービスを売るには顧客分析が欠かせません。こちらの記事では、マーケティングに欠かせない顧客分析について紹介いたします。
マーケティングに必須!顧客分析とは

顧客分析には大きく分けてCRM的なものとマーケティング的なものが存在します。
CRM的顧客分析
CRMとは、Customer Relationship Management(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)の略称になります。既存の顧客との関係と管理するための戦略を指します。普段特にB to Bのビジネスを行っている人は、顧客との関係維持のためにレスを早くするなどしていますよね。その戦略のことなのでイメージしやすいと思います。
マーケティング的顧客分析
会社の製品やサービスがどのような属性の人にニーズがあるのか、市場規模の将来性や可能性はどれくらいか、潜在顧客がどれくらいいるのかなどを探るものです。要するに、売るためにどういう人にアプローチを掛ければ良いのか戦略を立てるのかの指標の分析活動です。
例えば極端な例ですが、男性に女性用の化粧品を売りに行っても絶対売れませんし無駄な労力が掛かることになります。マーケティング的顧客分析を利用すれば、そういった無駄な顧客へのアプローチを無くしていけるのです。そうすれば顧客側としても、買いたくないものを売りに来られるストレスも無くなるので、マーケティング活動というのは双方がウィンウィンになります。今ではインターネットを活用した効率的な分析方法も多く発達しています。
ではここからは具体的なCRM的顧客分析の方法をこれから4つ紹介いたします。
マーケティングに活きる顧客分析:RFM分析

- Recency(リセンシー:購入時期)
- Frequency(フリクエンシー:購入頻度)
- Monetary(マネタリー:購入金額)
の頭文字をとって、RFM分析と言います。
Recencyというのが、最近購入した顧客のほうが何年も前に購入した顧客よりよい顧客と考えます。購入データのなかから「購入日時」を見て、その顧客が最後に買ったのがいつかを算出しグループ化します。Frequencyというのが、具体的には過去に何回自社のサービスや製品を買ってくれているかを出して、その回数が多ければ多い程重要度の高い顧客ということになります。Monetaryというのが、購入金額の合計が多い顧客程良い顧客だと考えます。高い商品やサービスを買ってくれる顧客を手厚くするのは、マーケティングの観点からも当たり前ですよね。
RFM分析では、これらそれぞれの指標を基に顧客の評価をして、重要な顧客なのかそうでない顧客なのかを見極めます。
そして3つの指標から総合的なスコアを算出し、
- 新規客
- 見込客
- 優良客
- 離反客
の4つのグループに分けます。
そして離反客以外の顧客に人的資源やお金を掛けます。そうすることで、重要な顧客に多くの時間を割くことができ、効率化が図れます。また、「新規客」「見込客」「優良客」の中でももし「新規客」のスコアが高いのであれば、新規客の目を引くような広告を打つというようなマーケティングにも応用ができます。
マーケティングに活きる顧客分析:CPM分析

CPM分析とは、Customer Portfolio Management(カスタマー・ポートフォリオ・マネジメント)の略称になります。日本語では顧客状態管理とも呼ばれます。
CPM分析では、セグメント分類を
- 購買行動
- 経過日数
- 頻度
に分けて考えます。
そして顧客層を
- 初回現役客:設定した期間内で初回購入実績のある顧客
- よちよち現役客:設定した期間内に2回以上購入実績のある顧客
- コツコツ現役客:設定した期間内で安定してリピート購入のある顧客
- 流行現役客:短期間で設定金額以上の購入実績のある顧客
- 優良現役客:長期間にわたって特定金額以上の購入実績のある顧客
- 初回離脱客:設定した期間内で初回購入後、離れてしまった顧客
- よちよち離脱客:設定した期間内に2回以上購入実績のあった顧客
- コツコツ離脱客:設定した期間内で安定してリピート購入があり、離れてしまった顧客
- 流行離脱客:短期間で設定金額以上の購入実績があり、離れてしまった顧客
- 優良離脱客:長期間にわたって特定金額以上購入実績があり、離れてしまった顧客
の10層に分けます。
こちらの分析手法はECサイトの運用において頻繁に利用される方法です。というのもECサイトの売り上げは8割から9割がリピーターなのですが、この分析方法はリピーターを増加させるマーケティングに向いているからです。それぞれの層の顧客に対して合ったマーケティングを行うことができれば、リピーターの増加が見込めます。
マーケティングに活きる顧客分析:デシル分析

デシル分析とは、顧客を購買価格が高い順番に10等分して考える方法で、マーケティング戦略を考えるのに役立ちます。デシルというのが、ラテン語で10分の1 を意味し、そこからきています。どの層の顧客がどれだけ売り上げに貢献してくれているかがすぐに把握可能です。非常に単純明快な分析なので、エクセルやスプレッドシートで簡単に作成できるのが特徴です。特段スキルを持たずに入社してきた一般事務の方でも可能なので、あまり人材確保が上手くできていない企業でも無理なくできます。
やり方としては、例えば1000人の顧客がいると仮定します。ある一定期間の購入金額の表を作成し、顧客を購入金額が高い順番に並べます。その後多い順に並んだ上位から100人ずつで、10グループに分けます。その後各グループの合計購入金額を出し、その各グループの購入金額が全体に対してどれくらいの比率になるかを計算します。例えば上位200人、つまり上位の2グループで売り上げの7割を占めていることが分かれば、その当該顧客をより大切にしないといけないのはもちろんのこと、悪い点としてはその顧客に売り上げを頼りすぎで安定性に欠けるとも言えます。そのためマーケティング戦略としては、あまり金額の使っていない顧客のアップセルを狙うことが考えられます。
マーケティングに活きる顧客分析:CTB分析

顧客を
- Category(カテゴリ)
- Taste(テイスト)
- Brand(ブランド)
でグループ分けをして、購買行動を予想する手法です。
Category(カテゴリ)はまたそこから大分類と小分類に分かれ、大分類では生活雑貨や食料品、小分類ではマグカップやウインナーなどに分けます。Taste(テイスト)はどのような模様やサイズ、デザインを好むかになります。Brand(ブランド)は小物のブランドメーカー毎に顧客を分ける形になります。
こちらの分析では、顧客がどのような商品を好んで購入するかを非常に高い精度で予想します。
良く「POS データ分析」と比較されますが、「POS データ分析」は売れ筋商品を割り出すのみですが、CTB分析では顧客がどんなものを購入したのか、どういった傾向があるのかという商品の更に具体的なものまで見えてきます。データに応じた売れると予測されるものを開発することや、ブランディング・マーケティング戦略を行うことで売り上げや利益の向上が見込めます。ただCTB分析に利用可能な情報を抽出する手段はあまり無いのが難点です。この分析を用いるには、オリジナルのシステムを組んだり、マネジメントを行う必要が出てきます。なので自社で豊富なエンジニア人材やマネジメントのスキルを持つ人間がいない場合は施行するのがかなり厳しいです。上級者向けの分析方法と言えるでしょう。しかしだからこそこちらの分析を確立できれば他社とかなり差別化を図ることができ、スペシャルなマーケティング戦略を実行できます。
▶参考:購買行動分析とは?これだけは押さえておきたい3つの手法とその特徴 についてはこちら
目的に沿った顧客分析でマーケティング戦略を練りましょう
以上のように顧客分析には様々な方法があり、方法によって達成できることは違います。リピーターを増やして利益を伸ばせるECサイトを運営しているのであれば、CPM分析を利用するのが良いです。人的資源が豊富にあればCTB分析に調整するのも良いですし、あまり余裕がない場合はデシル分析からマーケティングに着手するのも一手です。また顧客が多すぎて重要な顧客がどれか分からなくなっているのであれば、RFM分析で一旦重要な顧客を絞り込んで整理するのも良いでしょう。売上を上げるには顧客分析が必要です。どんなに良い商品を作っても、顧客のニーズに訴えない限りは売れないのです。自社の状況を客観的に把握し、正しい顧客分析方法を利用して、適切なマーケティング戦略を打っていきましょう。
無料ホワイトペーパー:オンラインとオフラインを融合したマーケティングの心得

オンラインとオフラインを組み合わせたマーケティングをどのように考えればいいのか分からないと悩んでいませんか?本書では、以下のことについて詳細に解説しております。
- オンラインに閉じすぎることによる弊害
- オンライン施策の売上効果に対する満足度は減少している
- オンラインとオフラインの特性の違い
- オンラインとオフラインの融合パターン
ぜひ、マーケティング戦略・戦術の策定にご活用ください。