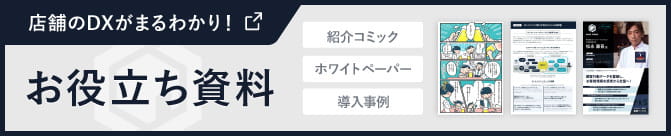人手不足が叫ばれる中、人材を積極的に採用している企業も多いですが、採用する際に問題が発生することがあります。
問題を防ぐためにも、人事担当者はトラブルの防止策・解決策を理解しておく必要があります。
今回はパートやアルバイトを採用する際に起きやすいトラブルについて防止策や解決策を含めて紹介していきます。
正社員、パート、アルバイト採用シーンでのよくあるトラブルとは?

一般的に採用シーンで起こるトラブルは大きく「入社前トラブル」と「入社後トラブル」に分けることができます。
入社前に起きるトラブル
入社前に起きるトラブルとしては次の3点です。
①面接に来ない
採用シーンでよくあるトラブルとしては面接当日になっても現れないことです。面接に来なければ応募者の良し悪しを判断する以前に、採用チャンスそのものを失いかねません。さらに、なぜ面接に来ないのかの理由が不明なため、今後の対策も出来なくなります。
②求人情報の誤り
応募者は求人情報をもとに、その企業に応募をします。求人情報がアップデートされておらず、実態に即していない求人内容であったり、細かな処遇条件が明示されていなかったりすることで、双方の認識がズレたまま選考が進んでしまうことがあります。
③内定取り消し
企業は正式採用前に「内定」という形で採用を約束する場合があります。この「内定」については内定承諾書を提出した時点で雇用契約は成立しており、内定を取り消すためには「相当な事由」(=健康異常の発生、犯罪行為など)が必要となります。反対に、正当な理由もないまま自社都合だけで「内定取り消し」を行うと不当解雇とみなされる恐れがあります。
入社後に起きるトラブル
入社後に起きるトラブルとしては次の3点です。
①入社日に現れない
入社後に起きるトラブルとして起きるのは、入社日に現れないことです。確信的に入社日に現れない方は連絡が取れないことが多いと言えるでしょう。採用から入社前準備を進めてきた企業にとっては損失が大きい上に、人手不足が解消されないので再度人員募集を行う必要が出てきます。
②経歴詐称
求人条件に「大卒以上」と明記しているのにも関わらず、実際は「高卒」だったという事例が極稀にあります。選考段階の履歴書では経歴詐称を行っていても、見抜くことは困難と言えるでしょう。深刻な経歴詐称の場合、解雇する必要も生じることから企業側にとっても大きな痛手となります。
③処遇条件の齟齬
求人票に記載されている処遇条件と実際に働いてからの処遇条件が異なっているとトラブルに繋がります。特に給与・休日・手当など重要な項目で祖語があった場合には離職に繋がるリスクが高まるだけでなく、最悪のケース裁判沙汰になる可能性もあるでしょう。
特にパート・アルバイト採用の際によくあるトラブルとは?

一般的な採用シーンにおけるトラブル事例は紹介した通りですが、次にパートやアルバイトを採用する際に起きやすいトラブルを紹介します。
パートやアルバイトを採用する際に最も頻繁に起きるトラブルは「労働条件の非提示」です。採用されたものの「時給以外の条件がわからない」「試用期間があるなんて聞いていなかった」など、働いてからでないとわからない条件が結構存在します。
実は正社員やパートやアルバイトに関わらず、人材を採用する際には必ず、「労働条件」を明示することが法律で義務付けられていますが、パートやアルバイトを採用する際に正しく労働条件が提示されずにトラブルに至るケースが多々あります。
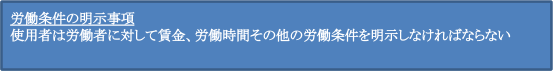
引用元:厚生労働省HP 労働基準法15条1項
労基法に明記されている文言は上記の範囲ですが、実際にパートやアルバイトを採用する際に明示しなければならない労働条件は次の項目です。
書面交付による労働条件
①契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)
②期間の定めがある契約の更新についてのきまり(更新の有無、更新する場合の判断基準など)
③どこでどんな仕事をするのか(就業の場所、従事する業務)
④仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇 、交替制勤務のローテーション等)
⑤賃金 はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払方法、締切と支払の時期)
⑥辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇事由を含む))
引用元:厚生労働省HP 学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表
また、この他にも「退職金の有無」、「賞与の有無」、「安全衛生」などの事項は口頭説明の義務があり、労働条件を正しく説明しなければパートやアルバイトとのトラブルに発展するだけでなく、法律違反にあたるので注意が必要です。
正社員、パート、アルバイト採用トラブルを防止・解決する施策とは?
ここでは採用シーンにおけるトラブルを防止・解決する施策を紹介していきます。
採用シーンにおけるトラブル事例に対する防止・解決策は次の通りです。
| 入社前 | 防止策・解決策 | |
| 面接に来ない | ・面接前のリマインド確認
・信頼できるエージェントの活用 |
|
| 求人情報の誤り | ・常に最新の求人にアップデート
・誤解を与えない表現にする |
|
| 内定取り消し | ・内定出しは慎重に行う
・内定取り消しに至る事由を明記する |
|
| 入社後 | 防止策・解決策 | |
| 入社日に来ない | ・内定後のフォロー
・内社前連絡の徹底 |
|
| 経歴詐称 | ・内定出し条件に卒業証明書の提出を義務付ける | |
| 処遇条件の齟齬 | ・労働条件を明確に通知する | |
| パートやアルバイト採用時 | 防止策・解決策 | |
| 労働条件の非提示 | ・労働条件を明確に通知する | |
トラブル防止のため正社員、パート・アルバイトに関わらず「労働条件通知」は必要

採用シーンにおいて多発するトラブルを未然に防ぐためには、パートやアルバイトであっても労働条件を正しく“書面”で(本人の同意があればFAXかE-mail可)通知する必要があります。
パートやアルバイトの採用だからといって、労働条件通知を怠ってしまうとトラブル発生のリスクは高まります。
例えば、飲食店の仕事はまとまった休憩が取りにくい業種ですが、「休憩時間」の条件を理解した上で、パートやアルバイトに予め通知しておかないと、トラブルに繋がりSNSへの拡散や最悪のケース裁判沙汰に発展します。
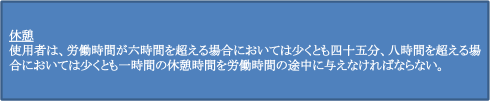
引用元:厚生労働省HP 労働基準法34条1項 ※労働時間6時間未満の場合は不要
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、必ず労働条件通知書を採用者に手渡すように心掛けましょう。労働条件通知書の作成方法がわからない場合は厚生労働省が推奨している「労働条件通知書のモデル様式」を使うことをオススメします。
パート・アルバイト採用の際によくあるトラブルとその防止策・解決策まとめ
今回はパートやアルバイトを採用する際に起きやすいトラブルについて防止策や解決策を含めて紹介しました。
せっかく貴重な人材を採用したとしても、入社前・入社後にトラブルが起きてしまうと人材の確保、人材の定着には繋がりません。
特にパートやアルバイトを採用する際に最も多いとされる「労働条件の非提示」は、採用されたものの入社してからでないとわからない条件が結構存在します。
実は人材を採用する際には必ず、「労働条件」を明示することが法律で義務付けられていますが、特にパートやアルバイトを採用する際に正しく労働条件が提示されておらず、トラブルに発展するケースが多くあります。そのため、採用シーンにおけるトラブル事例を知り、その防止・解決のための施策を理解することが非常に重要です。この記事を読んで、採用シーンにおけるトラブルを未然に回避していきましょう。